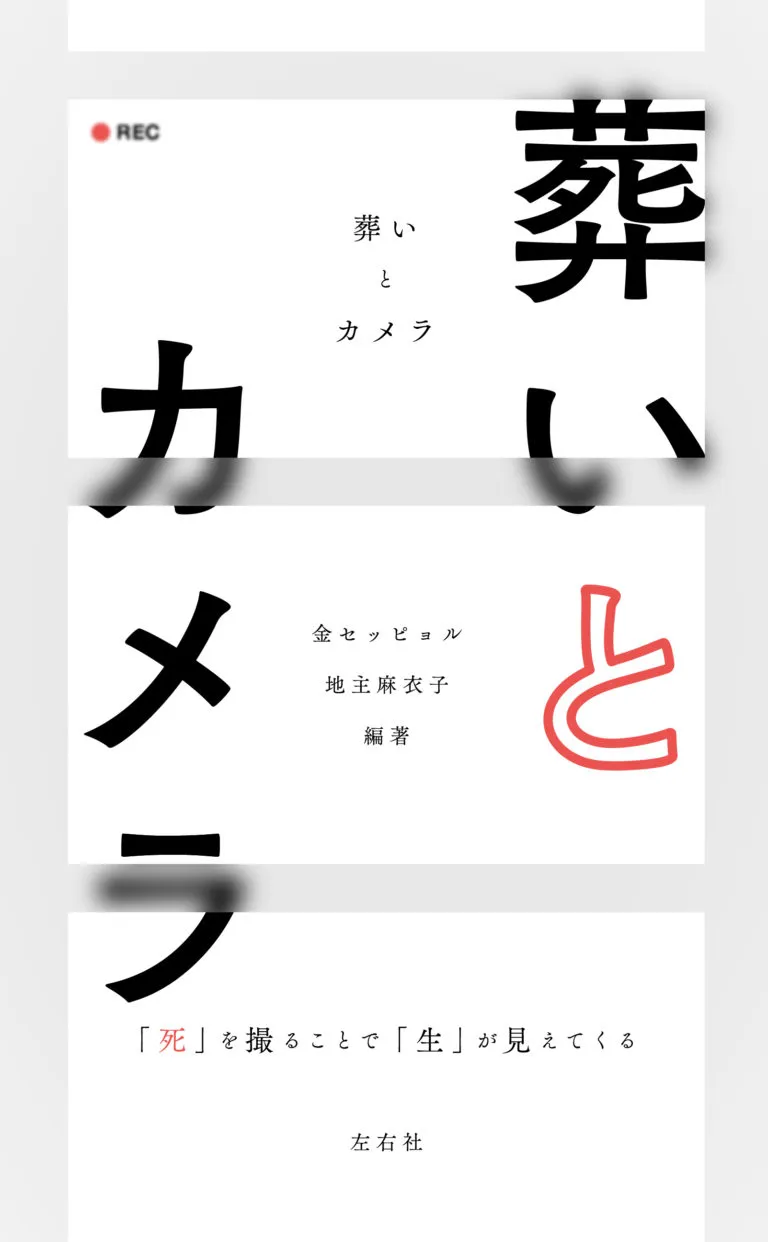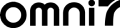書誌情報
- 定価
- 1,980 円(税込)
- ジャンル
- 芸術・デザイン・写真
- 刊行日
- 2021年05月30日
- 判型/ページ数
- 四六判変形 並製 200ページ
- ISBN
- 978-4-86528-031-9
- Cコード
- C0039
- 重版情報
- 2
- 装幀・装画
- 牧寿次郎/装幀
内容紹介
身寄りがなくなり、壊される無縁仏
自然葬をすることにした家族の葛藤
葬儀を撮ることの暴力性
在日コリアンのお墓
研究映像とアート作品
簡素化される葬儀と、葬いの個人化
誰もが直面する「死」と、残された者の「葬い」という営みを、どのようにとらえることができるのだろうか。
本書では主に映像によって記録するという行為を通じて、死や葬いを普遍的にとらえなおすことを試みるものである。
誰もがいつかは必ず直面する「死」という現象を、どのようにとらえたらよいのだろうか。
この本は、幸いにもまだ生きている私たちが「死」をどのようにとらえ、記憶、または記録していくのかということについて、アーティストと研究者がとことん話し合い、まとめたものです。
(「はじめに」より)